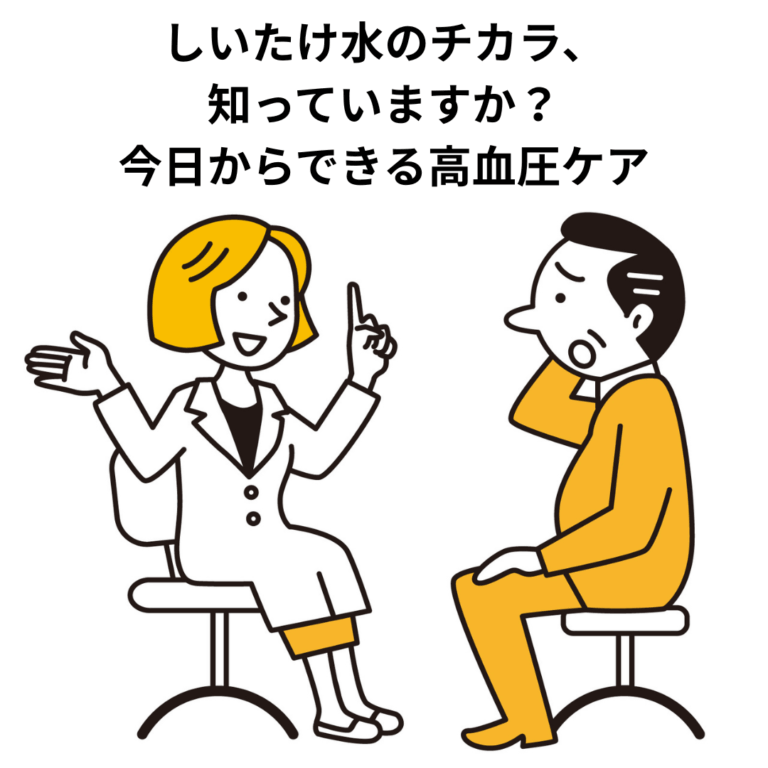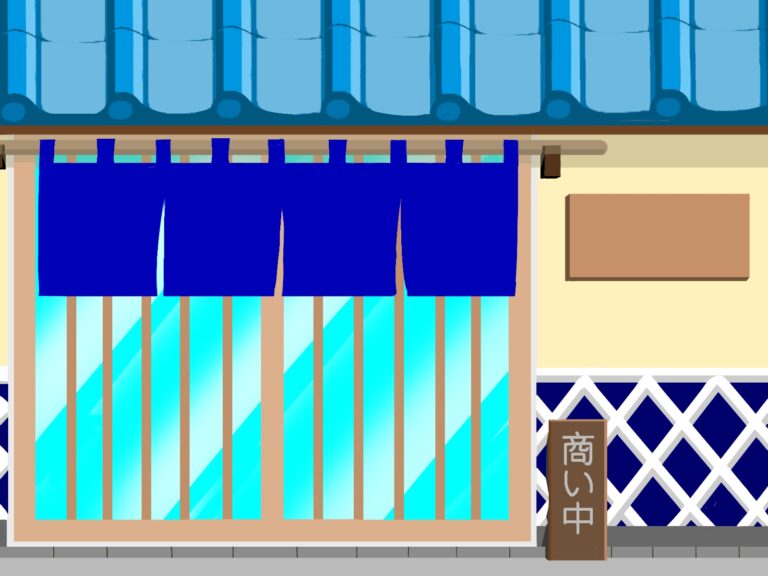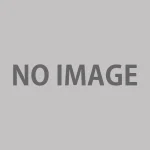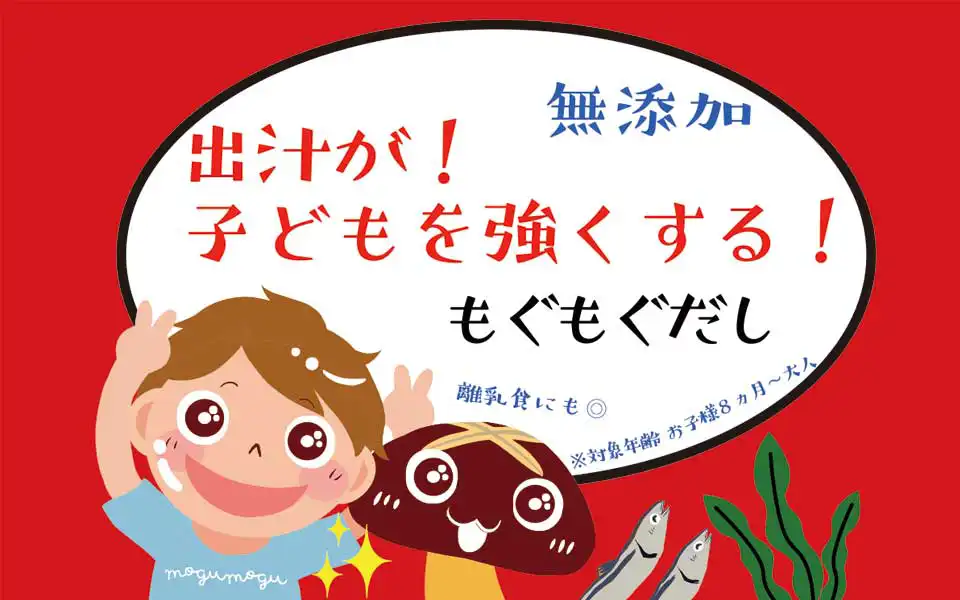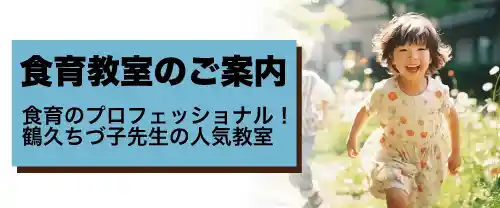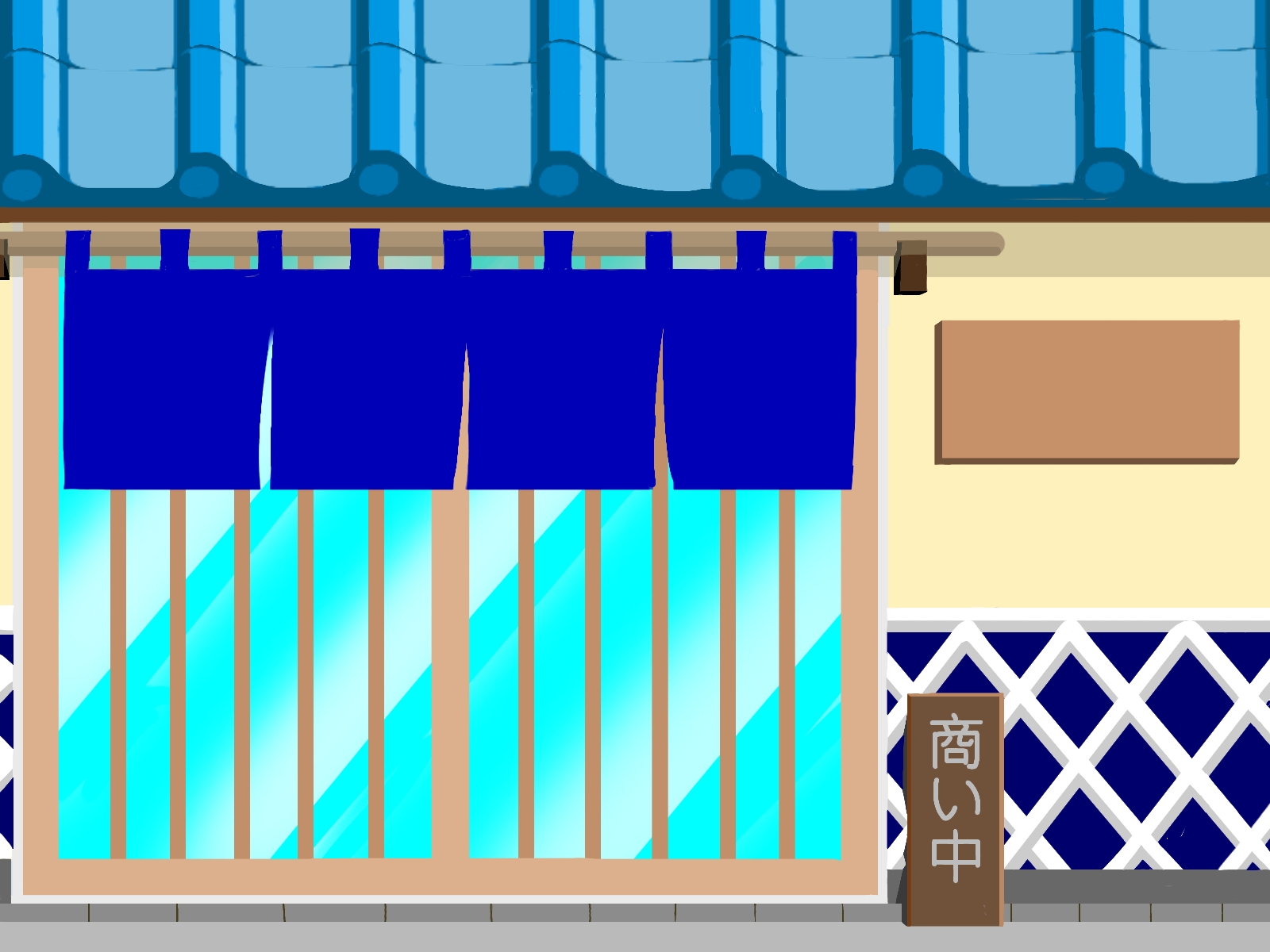
飲食店で使う食材は、味・香り・見た目すべてが勝負。
中でも「原木干ししいたけ」は、出汁の旨味、料理の格が一段と上がる特別な存在です。
でも、種類が多くてどれを選べばいいか迷うことも…。
今回は、飲食店目線で失敗しない選び方をご紹介します!

形
味に影響は少ないものの、しいたけの傘の形やふくらみは、料理の完成度を左右する“視覚的なおいしさ”に直結します。
おすすめの形はずばり「冬菇(どんこ)」です。
冬菇とは、傘が内側に巻いた状態のものです。
傘が丸まっているため、肉厚で弾力があり食べ応えが抜群です。
小さいサイズのものは、そのまま茶碗蒸しに入れてもGOOD!
冬菇しいたけは、煮物・姿煮・炊き込みご飯・和食の高級料理に最適です。

香り
出汁を重視する和食店・ラーメン店・鍋料理店では、香りの立ち具合も重要視したいところです。
原木しいたけは、自然のクヌギの木に菌を植えて2年がかりで育てられるため、木そのものが持つ香りと土壌の香りが凝縮されます。
これは、料理の風味を格上げすることができます。
春に採れる「春子」は、柔らかく上品な香りが特徴です。
そして、穏やかでまろやかな風味があります。
秋に採れる「秋子」は、香りが特に豊かです。力強く、深みのある芳醇な香りで料理の香り付けに最適です。
気を付けたいのは、油っぽい匂い。理由は、生しいたけを乾燥させる機械が古かったりする可能性もあります。

色見
しいたけを見ていると、「傘が濃いこげ茶のもの」と「白っぽいもの」があります。
「育て方の違い?」と思われがちですが、実はこの違いは種駒(たねごま)=しいたけの品種による場合もあります。
原木に植え付ける「しいたけ菌」のことを、業界では種駒(たねごま)と呼びます。
この種駒には、いくつもの品種があり、それぞれに「育ちやすさ」「香り」「肉厚さ」「傘の色」など特徴があります。
味の違いに大きな差はないものの、見た目を気にするなら白っぽいものが好まれる傾向があります。
使いやすさ
一般的に乾ししいたけの利用方法は、水戻しです。
8時間ほど水戻しをすると、十分にしいたけは戻ります。
ただ、時短やコスト重視の場ではスライス乾ししいたけもおすすめです。
戻さずに利用でき、炒め物やスープ、餃子などに利用するとGOODです。
ただし、時間をかけて戻すしいたけより香りや深みはやや弱くなります。
信頼できる産地・生産者か
国産原木、特に九州産・大分産などは高品質として日本そして世界に認められている食材です。
株式会社武久のしいたけもトレーサビリティ(生産管理、どこの誰がつくったかが追跡できるもの)やまた有機認証のしいたけも取り扱いを行っています。
こだわりの食材を選ぶ際はぜひ私どものしいたけをおすすめします。

まとめ
見た目の好みだけでなく、用途に合わせて形状やサイズを選ぶことが、料理のクオリティをワンランク引き上げます。
武久のしいたけは北は北海道、また海外のスーパーでもお取り扱いいただいております。
ぜひお気軽にお問合せください。